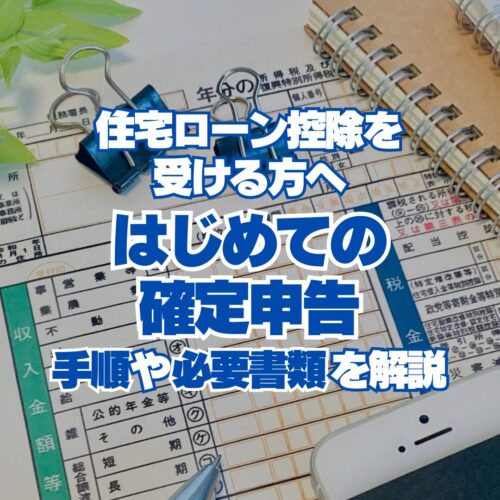今回は夫婦で組む住宅ローンについて、下記の4つの項目について紹介します。

1.夫婦でローンを組むにはどういう種類がある?
夫婦で住宅ローンを組む場合、主に以下の種類があります。
夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組む場合
共働き夫婦が二人分の年収を合わせて金融機関の審査を受け、一つの住宅ローンを借りる方法です。これを収入合算と呼び、一人分の収入で借りるよりも借入可能額を増やすことが可能です。収入合算はさらに連帯保証と連帯債務の2つのタイプに分けることができます。
⚪︎収入合算(連帯保証)
- 夫婦の収入を合算して、1本の住宅ローンを契約する方法です。
- 夫婦のうちどちらか一方が主たる債務者となり、もう一方は連帯保証人となります。
- 連帯保証人は、主たる債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する責任を負います。
- 連帯債務型に比べると、連帯保証人の責任はやや軽くなります。
- 借入可能額は、夫婦の収入を合算して審査されるため、単独で借りるよりも増える可能性があります。
- 住宅ローン控除は、主たる債務者のみが受けられます。
⚪︎収入合算(連帯債務)
- 夫婦の収入を合算して、1本の住宅ローンを契約する方法です。
- 夫婦のうちどちらか一方が主たる債務者となり、もう一方は連帯債務者となります。
- 連帯債務者は、主たる債務者と連帯して債務を負うため、主たる債務者と同等の責任を負います。
- 借入可能額は、夫婦の収入を合算して審査されるため、単独で借りるよりも増える可能性があります。
- 住宅ローン控除は、主たる債務者のみが受けられます。
- 団信は一人加入が原則。金融機関によって二人で夫婦連生団信に加入できるケースもある。
⚪︎ペアローン
- 夫婦それぞれが別々の住宅ローンを契約する方法です。つまり、一つの物件に対して二つのローンが存在する状態になります。
- それぞれの収入に基づいて審査が行われるため、単独で借りるよりも借入可能額が増える可能性があります。
- それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での節税効果が大きくなります。
- 互いに連帯保証人になるのが一般的です。 契約が二つになるため、手続きが煩雑になる、諸費用が二重にかかる場合があるなどのデメリットもあります。
共働き世帯であれば、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りることができます。ペアローンは夫婦それぞれの年収を基に審査されるので一人で借りるよりも合計の借入可能額を増やすことができます。ただしローンが2つになるとローン契約(金銭消費貸借契約)も別々になり手数料や保証料なども2つ分かかる点に注意が必要です。2人それぞれローンを借りることになるので、住宅ローン控除も二人それぞれに受けることができます。ペアローンの場合の団信は夫婦それぞれが加入することになるので、返済中に夫婦のどちらかが死亡した場合はそれぞれが借りていたローンだけが保険で完済され、もう一方が借りているローンはそのまま返済が続きます。
※夫婦連生団信について
夫婦連生型のメリット
- 残された配偶者の負担軽減: 最大のメリットは、どちらかに万が一のことがあっても、残された配偶者にローンの返済負担が一切残らないことです。これは、残された家族の生活を大きく支えることになります。
- 安心感の向上: 夫婦二人で安心して住宅ローンを組むことができます。
夫婦連生型のデメリット
- 保険料がやや高くなる: 通常の団信に比べて、保障が手厚い分、保険料がやや高くなる傾向があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるペアローンと収入合算ですが、すべての金融機関が用意しているわけではありません。実際には「住宅ローンを組む金融機関をどこにするか」で選択肢は限定されてしまいます。例えば、全期間固定型のフラット35を利用する場合は、連帯債務(収入合算)型を選択するしかありません。一方で、民間金融機関の住宅ローンにはペアローンしか用意されていないことがあります。金融機関や住宅ローンのタイプ、金利といった諸条件を複合的に検討して、借り方を決めることが大切です。
2.夫婦で住宅ローンを組む割合の適正値は?
住宅ローンを夫婦で協力して組む場合の負担割合については、各家庭の状況や収入に応じて適正値は異なりますが、一般的には収入の割合を考慮します。夫婦の収入に差がある場合、収入の多い方が多く負担するのが一般的です。例えば、夫が主として収入を得ている場合は夫がローンの多くを負担し、妻はそれに合わせた割合で負担することが考えられます。適正な負担割合は「収入比率」に基づきつつ、家庭の状況や将来のリスクを考慮して柔軟に決めることが大切です。
3.夫婦で住宅ローンを組む時の注意点は?
マイホームの購入にあたっては、夫婦の共有名義にして実際の資金の負担割合と同じ割合で持分を決め、「共有登記」をすることが原則です。夫婦のどちらかが購入資金を全額負担した場合でも持分を半分ずつにすることは登記上可能ですが、住宅の購入資金の負担割合と異なる割合で持分を登記すると、夫婦間の贈与とみなされて贈与税の対象となることがあります。出資額と持分割合を一緒にする場合、以下の計算式で求められます。
出資額÷不動産の価格=持分割合
具体例として、8,000万円の不動産を夫婦で購入した場合を考えてみます。8,000万円のうち、夫は6000万円を、妻は2000万円をそれぞれ負担しました。これを上の計算式に当てはめると以下の通りです。
夫 6,000万円÷8,000万=0.75
妻 2,000万円÷8,000万=0.25
このように、持分割合は夫が75%、妻が25%ということになります。しかし、持分割合は自由に決めることもできます。仮に持分割合を「夫婦で平等にしたい」として夫50%、妻50%と登記しようと思えば可能ですがこの場合夫から妻へ共有持分の25%(2,000万)の贈与があったとみなされてしまいます。持分割合は自由に決めることができる反面、意図しない贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
4.住宅ローンを夫婦で組む前に考えておきたい変化は?
働き方の変化
住宅ローンを組む際、働き方が変わることによって収入の安定性や将来のライフプランに影響が出てしまいます。また、共働きの夫婦でも子供が生まれたりすると、どちらかが家事や育児に専念する必要も出てきます。収入が一方のみになれば、家計が厳しくなるケースが考えられます。収入が変動する場合や支出が増減する場合、夫婦で話し合い、家計全体のバランスを見直すことが大切です。
夫婦関係の変化
夫婦が離婚する際、住宅ローンの負担やその後の住まいの取り決めに関してどのように対応するかは大きな問題になります。以下の点を考慮して、住宅ローンと離婚に関する問題をみてみましょう。
住宅ローンの名義と責任
住宅ローンの契約名義がどちらか一方であった場合、ローンの返済義務がその名義人にあります。しかし、離婚後もその負担が続くため、名義人がローンを返済し続ける義務を負うことになります。もし、ローン名義が夫婦両方であった場合、ローン返済義務は両者に分担されます。
もし離婚後も住み続けるために、ローン名義を変更したり、支払い義務をどちらかに引き継ぐ場合には金融機関と再交渉する必要があります。ローンの名義を変更するには通常、ローンの審査が必要となるため、再度信用情報をチェックされます。
ローンの名義人と保証人
住宅ローンの契約名義人が亡くなった場合、そのローンの返済義務が遺族に引き継がれるかどうかは、ローン契約の内容によります。通常、ローン名義人が死亡した場合、その残りのローンをどのように返済するかは残された家族がどのような契約を結んでいるかまたは相続の取り決めに依存します。
保証人の確認
住宅ローンには保証人が設定されている場合があります。この場合、保証人が返済を引き継ぐことになります。ただし、保証人がいない場合や補償内容によっては、遺族がローン返済の責任を負うことになります。
参考になりましたでしょうか?
夫婦で住宅ローンを組む場合は長期的の返済になるので、万が一のことがあったときの対応を話し合うことが大切です。
関連記事


 Instagram
Instagram YouTube
YouTube TikTok
TikTok